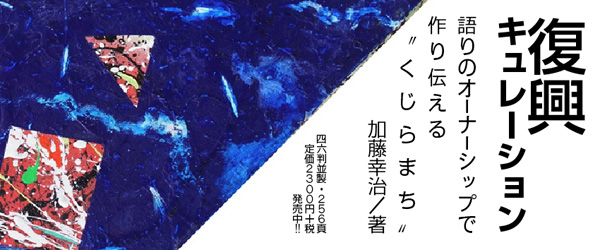
東北学院大学・加藤幸治氏の著作『復興キュレーション - 語りのオーナーシップで作り伝える〝くじらまち〟 (キオクのヒキダシ2)』より、冒頭の「はじめに」をお読みいただけます。(全5回)第1回 震災復興と人文学の葛藤
第1回
震災復興と人文学の葛藤
加藤幸治
(東北学院大学)
2011年3月11日午後2時46分。忘れもしない東北地方太平洋沖地震が発生した瞬間でした。三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震は、わが国の観測史上最大、世界規模でも20世紀に入って第4の規模の超巨大地震だったといわれています。地震の揺れや津波のみならず、原子力発電所の事故、交通遮断による物資流通の機能停止、ライフラインの断絶等によって多くの被害をもたらし、その規模は死者15894名、行方不明者2546名を数えます(2017年12月8日現在、警視庁まとめ)。そのうち宮城県の犠牲者は、全体の60パーセントあまりにのぼりました。また、この地震によって発生した津波は、三陸沿岸部で最大40メートル以上、仙台平野では海岸から最大6キロメートルあまりが浸水しました。津波で家屋が流されたり、原発事故で退避を余儀なくされたり、地震の揺れによる家屋が損壊したりして、7年が経過した現在でも7万5206人が避難生活を送っています(2018年1月6日現在、復興庁まとめ)。
東日本大震災から六年目の現在にいたるまで、被災地は動き続けています。震災1年目のあの困難な毎日。行く先の見えないなかで、復興への思いだけが先走っていた2年目。停滞感があせりへとつながりつつも、それが日常化していった3年目。嵩上げ工事等でかつてのくらしをしめす痕跡が土中に埋もれていくなか、復興後の地域社会のイメージをつめずに誰もが右往左往していた4年目。都市部を中心に復興公営住宅が林立していき、ハード面での復興を実感として感じはじめた5年目。復興の進度に地域格差が開いていくなか、どの地域においてもくらしの再建の着地点が見出せずにいる6年目。被災地の人々にとって、今ほど「私たちのくらしはどのようにかたち作られ、どこへ向かっていくのか」を、みずからの問題として考えたことはなかったのではないでしょうか。
研究者も暗中模索を続けてきました。最近では少なくなったものの、震災2年目、3年目はさまざまな分野で研究会やシンポジウムが開催されました。その多くは、「あの震災で何ができたか」を問題にしていました。目の前の課題に処方箋を出していくような社会科学や、社会の発展に必要なインフラを構築していく工学などと違って、人文学の多くは大震災後の混乱した状況のなかで無力感にさいなまれてきました。しかし、震災から五年が経過し、復興していく被災地の風景が、これまで見たこともない、まるで未来都市のような様相を呈してくると、人々はそこに生活を思い描けずに葛藤し始めています。地域の復興には、過去・現在・未来をつなぐ、そこで生きてきた生活の実感やくらしのイメージが必要とされています。
いつ役に立つかはわからないが、心の豊かさを求めて引き出しに“何か”を貯めていくような人文学にとって、復旧期から復興期に移行していく今がまさに正念場です。人々が、災害というインパクトを乗り越えて過去と現在をつないでいく「ひとり一人のくらしの風景」を、心のうちにどのように抱くことができるか、設計図のような理論よりフィールドでの実践が求められています。わたしが専門とする民俗学という学問は、フィールド・ワークを通じて地域の人々と長期的にかかわりながら、人々の生活の歴史を民俗誌として表現します。そこからはじめて何かを語り始めるようなところがあり、正直なところ震災6年目の現在にあっても「あの震災で何ができたか」を論じる材料には乏しいのです。本書『復興キュレーション』で読者のみなさんにお伝えしたいのは、東日本大震災から現在まで、文化財レスキューを出発点として被災地に関わりながら、「ひとり一人のくらしの風景」を紡ぎだしていくための取り組みと、そこから生まれる様々な問いについてです。
わたしは民俗学者であると同時に、ミュージアムを通じて民俗研究を市民社会に位置付ける活動を研究の主軸に置いている“博物館屋”です。被災地は文化創造活動における最前線のフィールドであり、そこでのすべての活動がフィールド・ワークです。被災地でのくらしの営みは、目の前のイレギュラーな状況に対するその場しのぎの対応の連続です。しかし、そこにある問題は、「被災地の課題」としてみると特異な状況に見えますが、問題の本質は被災地にとどまらないものがほとんどです。イレギュラーな状況にあって、普遍的な問題が先鋭化して見えやすくなっているにすぎないのです。現場に寄り添いながら問いを見出すのがフィールド・ワークの本分だとすれば、被災地での実践から見えてくるものは現代社会がかかえる、文化をめぐる様々な課題です。
こうしたスタンスを大切にしながら、わたしはミュージアムのコレクションの復旧と、博物館活動を通じた復興への積極的な関与という、二つの面で仕事をしてきました。本書では、このふたつの内容において、現場で考えてきたことを提示していこうと考えています。

購入サイト(外部リンク)
投稿者: 社会評論社 サイト
社会評論社 SHAKAIHYORONSHA CO.,LTD. 社会評論社 サイト のすべての投稿を表示